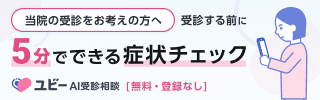・血液検査で腎臓の値(クレアチニン)が高い
・家族で腎臓が悪い人がいる(透析になった人がいる)
・尿検査でたんぱくが出ている
・尿検査で血尿が出ている
・腎臓にのう胞や石がある
・腎臓のせいでむくみがある
・頻尿で困っている
様々な内容があり、該当する方は意外と多いのではないでしょうか。
上記でお困りの皆様には、腎臓の精密検査をおすすめします。
腎臓の機能は、「クレアチニン」で評価するのが一般的です。クレアチニンをもとにeGFR、クレアチニンクリアランスなどを算出し、その値で腎臓の機能が低下しているかどうかを評価します。一方で、クレアチニンだけでは、筋肉量や薬の影響で正確な評価ができないこともあるので、当院では「シスタチンC」を用いたeGFRも算出して、本当の腎臓の値を検査します。
腎臓のもう一つの重要な指標が「尿たんぱく」です。尿たんぱくの量が多いと、腎臓の機能は悪くなりやすいことが知られています。健診などでは、尿たんぱくを(+)や(-)で評価していますが、当院では、一日当たりどれくらいの量のたんぱくが尿中に出ているかを調べます。この尿たんぱく量は、腎機能の予後評価、治療効果の判定、薬の調整などに非常に有用です。
その他に、尿中の赤血球などの成分を顕微鏡で見る検査や、NAG、β2MG、L-FABPなどの物質を測定することで、腎臓のどの部分が障害されているかを推測します。
腎臓の形態も重要であり、超音波検査やCT検査による評価も行いますが、腎臓病の正確な診断には、腎臓の病理検査(腎生検)が必要不可欠です。最適な治療の選択のために必要に応じて連携先の病院に腎生検の検査入院を依頼することもあります。
腎臓病においても塩分摂取量は重要であり、まずは適切な塩分摂取を指導しています。尿検査で1日の塩分摂取量を計算できるので、外来では毎回測定します。
腎臓の機能は加齢により、徐々に低下する傾向にあります。薬剤や脱水などの影響も受けやすく、自覚症状なしに進行します。尿中のナトリウムなどを測定して、脱水の有無を確認したり、適切な利尿剤の量に調整したりします。
たんぱく尿があると腎臓の機能は低下しやすいので、たんぱく尿を減らす治療が有効です。現在は、腎臓の治療薬として、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬「ARB」や「SGLT2阻害薬」が主流です。その他に、腎臓の機能が低下すると、Kを下げる薬(ロケルマ、カリメート)、腎性貧血を改善するエリスロポエチン製剤や「HIF-PH阻害薬」、リンを下げる薬、ビタミンD製剤、重曹などで腎臓のはたらきをフルサポートし、負担を軽減することで、腎臓の機能を長持ちさせることができます。
当院では、透析予防のための治療を継続することができます。腎臓専門医、透析専門医、移植認定医の資格をすべて取得しているからこそ、腎臓についてとことん付き合うことができます。セカンドオピニオンや腎臓の先生に相談したいなども気軽にご相談ください。